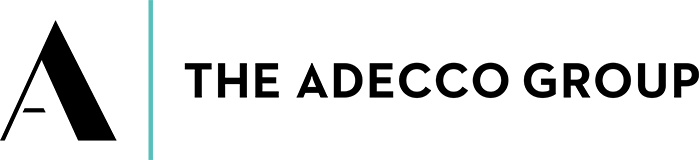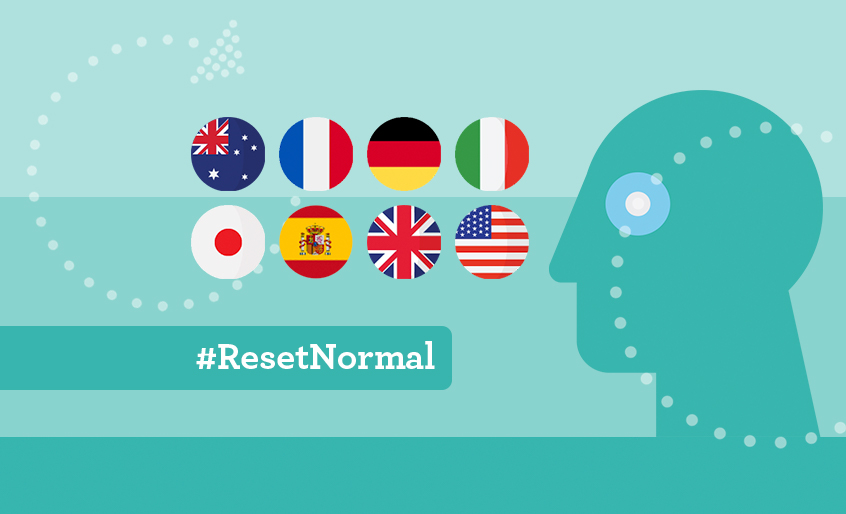テレワークが普及したことは、働き方の自由度を高める大きな契機となった。
今後は私たち一人ひとりが、特定の場所や時間にとらわれず、自分の価値観や仕事内容に最もふさわしいワークスタイル・ライフスタイルを選んでいく時代になるだろう。
『ワークスタイル・アフターコロナ』の著者であり、コミュニケーション・デザインなどの観点から新しいワークスタイルのあり方について研究している関西大学社会学部教授の松下慶太氏に、アフターコロナに向けて今後予想される働き方の変革(トランスフォーメーション)について聞いた。
コロナ禍は「働きたいように働ける社会」を目指す契機
言うまでもなく、コロナ禍は働く私たちの仕事観や人生観に多大な影響を与えた。特に若い世代ほど、コロナ前後でその価値観は大きく変化したようだ。Adecco Groupが2021年5月に実施した『コロナ禍の人生観・仕事観に関する調査』によると、コロナ禍の前後で自身の仕事や働き方についての考え方が「変わった」「ある程度変わった」と答えた人の割合は、50代では25.1%であるのに対し、20代では38.6%と大幅に上回った(図1参照)。具体的には、「働き方(時間・場所など)」や「キャリア形成」「仕事へのモチベーション」が変わったという回答の割合が大きくなっている。
図1
コロナ禍前後での、仕事や働くことの考え方の変化
■変わった
■ある程度変わった
■あまり変わっていない
■変わっていない
■今後の仕事や働くことについて考えたことがない
出典:Adecco Group「コロナ禍の人生観・仕事観に関する調査(2021年5月)」より
こうした働き手の価値観の変化は、企業側にもさまざまな影響を及ぼすと考えられる。最もわかりやすいインパクトを与えそうなのが、「リモートネイティブ」の存在だと松下慶太氏は話す。リモートネイティブとは、2020年4月以降に企業に新入社員として入社、あるいは大学に入学して勤務や授業をオンラインからスタートさせた年代層のことだ。
「例えば私の勤務先である関西大学の場合、受講者200人以上の講義はすべてオンデマンド方式になっています。200人以上が一堂に会して講義を聞く経験を、現在の1、2年生はほとんどしていません。リモート環境でスタートした学生たちに、対面で講義しようとする場合、今まで以上に高いクオリティが求められます。わざわざ大学の講義室まで足を運んでくれたわけですから、こちらはオンデマンド以上の魅力的な講義を提供しなければならないからです。それができなければ、そっぽを向かれてしまうでしょう」
今後、リモートネイティブたちが新入社員として入社していくと、企業も同様の課題に直面すると考えられる。
「人と人が対面で接することには、オンラインとは異なる価値があるのは間違いありません。とはいえ、リモートに慣れ親しんだ世代からすれば、オンラインでも十分事足りるような会議に対面で出席させられたりしたら、不合理だと感じるはずです。テレワークに消極的な企業は、そもそも就活で選ばれなくなる可能性すらあります」
この1年余り、リモートネイティブに限らず、さまざまな世代がリモート環境を経験した。いずれコロナが収束すれば、オフィス勤務や対面コミュニケーションが復活していくだろうが、皆がリモートの利便性をそれなりに体感した以上、昔の働き方に単純に戻るとは考えにくいと松下氏は言う。
「誰もが同じ時間帯に出勤して同じ空間で働くスタイルは、社員の個性を発揮させるのには不向きで、すでに限界を迎えていたと思います。私たちは今回のコロナ禍を、『みんなが働きたいように働ける社会』をつくる大きなチャンスだととらえるべきです」
WFH(Work From Home)からWFX(Work From X)へ
2020年春以降、海外では欧米メディアを中心に、在宅勤務を前提とした働き方を『WFH(Work From Home)』と呼ぶようになった。これに対し、松下氏は『WFX(Work From X)』という概念を提唱している(図2参照)。
図2
コロナ禍のWFHからニューノーマルのWFXへ
| |
WFH
Work From Home |
WFX
Work From X |
| モード |
非日常・強制的 |
日常的・選択的 |
| 働く場所 |
自宅 |
今いる場所 |
| 分散の仕方 |
小さいor ない |
大きい |
| 仕事の進め方 |
既存の代替 |
リモート最適化 |
| コントロール |
管理職や会社から |
自分で自主的に |
| セレンディピティの余地 |
小さい |
大きい |
出典:松下慶太著『ワークスタイル・アフターコロナ』より
「オフィスや自宅だけでなく、コワーキングスペースやサテライトオフィス、さらにはワーケーションなども含めて、働く場所のバリエーションがどんどん増えていくイメージです。働き手一人ひとりが多様な場所から働くことで、自分に合った新しいワークスタイルを生み出しやすくなりますし、偶然誰かに出会ったり、予想外の発見をするセレンディピティの余地が大きく、イノベーション創出につながりやすいと期待できます。Xには“働き方のトランスフォーメーション” につながるという意味合いも込めています」
WFXでは、働き手が自分のワークスタイルを主体的に構築していくことができるし、それが求められる働き方でもある。しかし、これまでの日本のビジネスパーソンはオフィス勤務が大前提で、自分の仕事や価値観に合った働き方を創造していく姿勢が乏しかった。
「育児中の人が保育園に子どもを送りやすいよう、午前中は自宅で仕事をするというスタイルはもちろん、花粉症で悩む人が、春先だけ花粉の少ない北海道や沖縄で働くスタイルを選んでもいい。みんなが働きたいように働けるとは、そういうことです」
自分のスタイルをどう見つけるか「3つのS」がヒントに
ワークスタイルを自らデザインしていくには、自分が何を大切にしたいのか、価値観やライフスタイルを見つめ直すことが必要になる。ワークスタイルの方向性を見出す指針として、松下氏は「3つのS」を挙げる。
①「Stimulate =刺激」
在宅勤務でも、自宅の周辺を散歩したり、家事・育児をしたりするなかで新しい発見があるかもしれない。オフィス勤務の場合も同僚との会話や通勤の移動時間のなかで仕事や生活に関するヒントを得られることがある。コワーキングスペースやワーケーションを利用した働き方を選べば、より新鮮な出会いや発見があるかもしれない。こうした刺激がなければ、退屈した毎日を過ごすことになってしまう。自分が日常的にどんな刺激を得たいのか考えることは、ワークスタイルを構築していく大切なヒントになる。
②「Story =共感できる物語」
私たちのワークスタイルは、仕事の内容であったり、取引先や消費者であったり、仕事を取り巻く環境や社会課題であったり、さまざまな共感によって形づくられており、それが私たちの仕事のやりがいにつながっている。どこに自分の共感できる物語があるのか、それをより充実させるには何が必要かを突き詰めていくことも、自分にふさわしいワークスタイルを考える指針になるはずだ。
③「Sustainable =持続可能性」
大規模な自然災害やパンデミックに直面しても出社を余儀なくされる働き方は持続的とはいえないし、逆に自宅にずっと引きこもるような働き方も持続するのは困難だ。人生100年時代を迎え、自分にとってどんな働き方が持続可能なのか、考える視点が重要になる。
「このように自分のワークスタイルやライフキャリアを自律的に見つめ直し、価値観を棚卸しするような作業は、日本ではあまり重視されてきませんでした。今後は働く一人ひとりが振り返りの時間を持つことが大切です」
また考えるだけでなく、とにかく実践してみることも重要だと松下氏は強調する。その際、「重ねる」という発想がポイントだという。
「これまでのワークライフバランスは、仕事の時間をどれだけ減らして家庭の時間をどれだけ増やすか、つまり足し算・引き算の話になりがちでした。そうではなく、多様な時間を重ねてみる。例えば夫婦2人が自宅でテレワークをする場合、一方は食事をつくりながら、もう一方は子どもの世話をしながら仕事したりするわけです。あるいはワーケーションであれば、何か趣味や娯楽をしながら仕事をする。では、何と何を重ねるとうまくいくのか。
子どものいる自宅でのテレワークは大変といいますが、実際にやってみたら、子どもたちは親の働くかっこいい姿を見られて、教育的に良いかもしれないし、家族関係にもプラスに働くかもしれない。こういう重ねる発想にわれわれは決定的に慣れてない。ワークとライフを分けるのではなく、重ねることを実践しながら自分に合ったスタイルを見つけてほしいですね」
オフィスは井戸型から焚き火型へ 企業側には何が求められるか?
一方、企業側には今後、働き手が独自のワークスタイルを形成していくのを支えるような役割が求められる。前述のように、リモートネイティブが増えていくことを考えれば、報酬の高さや福利厚生の充実度だけでなく、どれだけ柔軟なワークスタイルを提供できるかが、選ばれる企業になるための条件となっていくと想像できる。
参考になりそうな考え方として松下氏は、このほど米グーグルが発表したハイブリッド型勤務を挙げる。同社は2021年5月、より柔軟なワークスタイルを取り入れるため、1週間のうち3日をオフィス勤務、2日は社員にとって最適な場所からの勤務を認める「ハイブリッド型」を導入することを明らかにした。さらに夏季や年末年始のワーケーションを想定して、1年のうち4週間は、マネジャーの承認を条件に、どこからでも勤務できるようにしている。
「グーグルは社員全体の2割は恒久的テレワークに、6割はオフィスやテレワークを併用したハイブリッド型勤務に、残りの2割は別のオフィスでの勤務に移行すると想定しています。当然、どんな企業でもグーグルのようになれるわけではなく、エッセンシャルワーカーに代表されるように、テレワークが難しい業種や職種もあるわけですが、とはいえ『何が何でも週に5日出社しなさい』というスタンスでは企業は選ばれにくくなる。グーグルの例を参考に、自社であれば週の何日ぐらいまでハイブリッド勤務を認めるのがいいだろうかと、自社が提供できるワークスタイルを検討していくのがよいでしょう」
ワークスタイルが変わるのに伴い、企業のオフィス環境も抜本的な見直しが求められる。「今後は“井戸”的なオフィスから“焚き火”的なオフィスへのシフトが進むはず」と松下氏は話す。
図3
「井戸的」オフィスと「焚き火的」オフィス
出典:松下慶太著『ワークスタイル・アフターコロナ』より
井戸的オフィスとは、生活に欠かせない水をくむために井戸に行くように、仕事に欠かせない施設を利用するために行く場を意味する。これまでのオフィスの役割の大半は井戸的だったが、デジタル化やモバイル化、ネットワーク化が進み、オフィスで働く必要性は薄れている。
「一方、私たちが焚き火に求めるのは、調理したり暖をとったりする機能性だけではありません。焚き火を囲んで会話をしたり、喜びや楽しさを皆で共有したりする意味合いがあるはずです。焚き火的なオフィスとは、仕事に必要だから行く場ではなく、社員同士のコミュニケーション機会を提供し、関係性を深めるための場を意味しています。選ばれる企業になるためにも、短期的な生産性や効率性だけでは測れないこうした価値に着目して、オフィスの見直しに積極的に取り組んでいくこともより重要になるでしょう」
Profile
松下慶太氏
関西大学社会学部 教授
1977年神戸市生まれ。博士(文学)。京都大学文学研究科、フィンランド・タンペレ大学ハイパーメディア研究所研究員、実践女子大学人間社会学部専任講師・准教授、ベルリン工科大学訪問研究員などを経て現職。専門はメディア論、コミュニケーション・デザイン。近年はワーケーション、コワーキングスペースなど新しいワークプレイス・ワークスタイルと若者、都市・地域との関連を研究。近著に『ワークスタイル・アフターコロナ』(イースト・プレス、2021)など。
note:https://note.com/matsulab