戦時中に成立した日本の人事評価制度
「現在の日本の人事評価制度の基礎ができたのは、第二次世界大戦中であると考えていいでしょう」。そう話すのは、国内外の人事制度に詳しい東京大学教授の大湾秀雄氏である。大湾氏によれば戦前の日本では、定期昇給制度の確立に合わせ何らかの評価制度が形成されたと見られるが、ブルーカラーの処遇は職務給を基本としつつも、"えこひいき"に満ちた恣意性の高いものだったという。
「大きな転機があったのは、戦争が始まり、労働者が徴兵されるようになってからです。企業間で働き手の奪い合いが生じると考えた当時の政府は、転職を制限する政策をとりました。ほかの会社から働き手を招きにくい状況になった企業は、一人の社員が複数の職務をこなす、いわゆる「多能化」によって人員不足に対処しました。同時に、ホワイトカラーとブルーカラーの垣根を取り払い、生活保障給の仕組みを導入。年齢、勤続年数、家族構成などによって賃金を決めることとしたのです」
こうして会社は、「生活に必要な賃金」を社員に支給し、社員はその会社であたかも家族の一員のように保護されるという日本型の雇用慣習の原型が成立した。
90年代まで続いた生活保障給型賃金
市場メカニズムが働かないこのような仕組みは、生産性と賃金が乖離するという大きな問題を抱えていた。戦後の経済成長の中で、次々に新たな技術が導入され、仕事の進め方も日々刷新されていったが、ある程度の年齢に達していた社員は、それについていけず、生産性が賃金を下回るというケースも出てくる。しかし生活保障給型の賃金システムにおいては、生産性に連動して賃金を下げるわけにはいかない。労働力不足や資本自由化を背景に競争力低下の懸念に危機感を強めたのが、当時の日経連(現・経団連)だった。1969年、日経連は『能力主義管理──その理論と実践』において、(1)職能ごとの資格制度の導入 (2)能力開発の機会の提供 (3)資格等級と役職等級の分離といった制度を提案した。
この提案は70年代から80年代にかけ多くの日本企業で導入されたが、異なる職能間の人事異動も多かった日本では、職能別の資格制度は実現せず、人事部門による年功的な一元管理の仕組みがその後も残った。「みなが一律に昇格し、8割以上が課長になる」という慣習は90年代初頭まで続くこととなる。
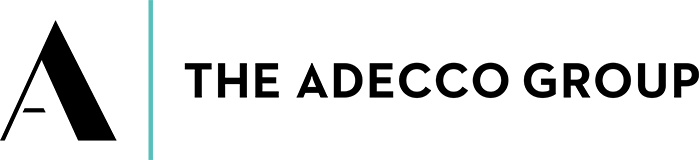
![【図1】 変遷図 [戦前]職種により異なる評価制度、異なる賃金体系](/-/media/images/adeccogroup/power_of_work/vistas/adeccos_eye/31/index_c_1_img_01.gif?la=ja-jp)
![[戦中]職種の垣根を取り払い、生活保障給を導入](/-/media/images/adeccogroup/power_of_work/vistas/adeccos_eye/31/index_c_1_img_02.gif?la=ja-jp)
![[戦後/高度成長期]「後払い賃金」制を柱とする日本型年功制の確立](/-/media/images/adeccogroup/power_of_work/vistas/adeccos_eye/31/index_c_1_img_03.gif?la=ja-jp)
![[戦後/バブル以降]市場成長にかげり日本型年功制の維持困難に](/-/media/images/adeccogroup/power_of_work/vistas/adeccos_eye/31/index_c_1_img_04.gif?la=ja-jp)
