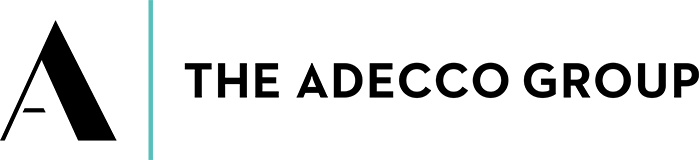「私がイクボスを推進するのは、仕事と育児、プライベートなどを両立することで社員の能力とモチベーションが向上し、結果として会社の収益性もアップするからです」
そう語るのは、"元祖イクボス"として知られる三井物産ロジスティクス・パートナーズ社長の川島高之氏だ。川島氏は子どもが生まれた33歳のときから妻と育児をシェアし、毎朝食事を作って保育園へ送り迎えをする"イクメン"だった。
「残業しなくなり、勤務時間は3分の1ほど減りました。でも勤務時間が減ったからといって成果を落とすわけにはいきません。むしろ、会社に長くいていつでも対応してくれる人のほうがどうしても評価は高くなりがちなので、私はその人たちの倍の成果を出すことを目標にしました」
これを実現するために、通常は顧客の元へ3回通って了承を得るところを、事前に綿密な商談の戦略を立て、1回でまとめるようにするなど"1回集中型"の仕事スタイルに変更。移動時間や子どもをあやしながら資料を読んだり勉強したりと、"すきま時間"も徹底活用したという。